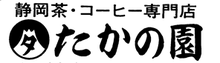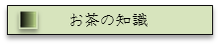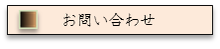三浦雅士著『出生の秘密』を読み、私自身の生き方も含めて、人間は『幼児期の生まれと育ち方』に翻弄され一生を過ごすことに納得させられます。
私自身が二十歳頃から読書を始めた理由も、理不尽で私には理解できなかった父を知るための心理学の本がきっかけでした。
孫が私と楽しそうに遊んでいる時、今は『何の為に生きているのか?』など考えていませんが、成長と共に悩み苦しむような人格の軋みに揺さぶられる時、出生のルーツと承認による自己肯定感の有無が大きく作用します。
暗い出生の秘密に鋭敏な感受性が重なった時、作家や芸術家としての偉大な才能開花に繋がると想像していましたが、実は逆で『三つ子の魂百まで』のように出生の秘密が鋭敏な感受性を育てています。
『事実は小説よりも奇なり』と言いますが、志賀直哉は母と祖父との不義の子で、『暗夜行路』文中に実父と相撲をとり息子が完膚泣きまでに叩きのめされ、最後に手足まで縛られた場面は実父の祖父への憎しみが息子向かった表現と想定されます。
別な本で知った島崎藤村は実兄の娘、つまり姪を孕ませ妻にしており、中島敦は実母の愛を知らないで育つうちに、父は再々婚をし異母兄妹の中で育っており、デカルトも母を知らず祖母と乳母に育てられました。
このような出生の秘密は、己の生への不確かさと不安を生み続けるのですが、子供の頃からその手がかりになるものに懐疑を持つために鋭敏な感受性が育ち易く、その懐疑と感受性に理知的な教養が加わって紙一重の天才が開花するものと思います。
失ったものが大きい代わりに、大きなものを得ている皮肉を感じますが、大人になり俯瞰した眼で克服できる人と、大人になっても直視できず、幼少時の鋭利な刃物のままの感受性で自己肯定感が持てずに、良い作品には繋がっても三島由紀夫や芥川龍之介のように最後は自殺という結末になる二通りに別れます。
人間は自分の無知と誤りを知ることで、揺れ動きながら自分自身になるのですが、そこで大切なことは『自分が何者であるかを決めているのは実は他人の言葉』であり、自分自身になる為の真理も論理のような学問ではなく、人生における体験的な直感によってしか得られないのが人間です。
ところが現在の日本は学歴という論理優勢だから、不祥事が増え自殺が減少しないのだと思います。
全ての人間に存在する出生の秘密や境遇の秘密が煩悩の原点にあり、その克服の参考にと思い二人の有名作家の出生の秘密を例に取り上げ考えてみます。
芥川龍之介は実母・養母・叔母・義母の四人の母によって、幼少期に複数の現実を押し付けられる経験をしました。
実母は芥川を生んですぐ狂気になったので母の兄に引き取とられ、兄の妻が養母で一緒に住んでいた叔母に溺愛されましたが、この叔母が拠り所と共に負担に感じた矛盾と、自分を生んで狂気に陥った母を知り、自分は生まれなかった方が良かったのでは? という懐疑を持ち続けた結果、独特のシニシズム(社会風習や既存の価値や理念に対して懐疑的に冷笑する態度)に陥ったようで、その後に実母の死去で実父が再婚し継母のいる父のもとに戻っています。
芥川が生きていくには出生の秘密である現実を相対化し、自分自身の現実を作り上げないといけないのですが、封印し続けたために他者を批判して優位に立とうとする強迫観念から最後まで逃れられず、必然として孤立がより深まり言い知れぬ寂しさや不安を払拭できず、いつまでも安住できない精神的に不安定な状態が続きました。
無意識領域にある出生の秘密への僻みが、反動としていつも他者に対し批判・冷笑・軽蔑などの言動で優位に立とうとする観念に支配され続けていました。
特に理知的な人に訪れる不幸は、自殺に繋がる『爆薬を抱えている』人ほど、批判と拒絶の冷笑主義的な振る舞いが多いので、結局回りの人達に拒否され孤立に繋がる連鎖を繰り返し、現状に安住できない不安定な精神状態の悪循環に陥っています。
芥川はこの寂しさや不安の源である火薬庫に蓋をして虚勢を張っていたから、自分の誕生が母の狂気に繋がったという重荷から最期まで逃れることができませんでした。
人は誰でも何がしかの秘密を抱え蓋をして生きているのですが、いつかはその蓋を自らの力で開け、自分自身が絶対化しているものを相対化しないと、トラウマからは解放されず悩み苦しみ続けてしまいます。
芥川が蓋をして避け続けた証拠になるのが、彼の作品には『愛と性の世界』が欠落していることで、愛を相対化することへの恐れを最初は無意識に、成人してからは意識的に母性愛という出生の秘密から逃げ続けていたからで、三島由紀夫(かなり昔のブログに記述したので省略)も同様のものを抱え続け自決しました。
同様の出生の秘密を抱えていた夏目漱石の場合は、母が『こんな歳で懐妊したのは面目がない』と言って、貧乏な古道具屋に里子に出され店先の籠に入れられ晒されて育ち、二年後にまた養子に出されましたが、やがて養子先と実家のゴタゴタの末の六歳頃に実家に戻っています。
そのトラウマ現象は、捨て猫を客観視して書いた『我輩は猫である』など初期の作品に出ており、その猫は最後に酩酊して溺れ死ぬのですが恐らくその時は覚悟の自殺を意識した記述です。 『坊ちゃん』なども孤児になった男の話で、『虞美人草』は私生児と継子の物語で、小説家にとって作品とは自分自身の無意識の謎を、意識的に探求しているものです。
漱石も『自分は生まれない方がよかった』と考え卑屈になり僻んでいたのですが、しかし漱石は吐血するまで卑屈が傲慢に転じる典型の生活の中で過ごしておりました。
漱石死後の妻の本を読むと、漱石による卑屈・僻み・傲慢の苦しみ記述が多くありますが、『妻に望まれてここにいていいよ』という言葉を求める駄々っ子の僻み言動ばかりで、愛されなかった母への渇望を妻に求めていた言動そのものです。
人間は辛い経験で非人情を知るのですが、その経験を直視して己をも見つめないと、自分が渇望し求めている人情に決して行き着くことはできないと思います。
漱石の初期五年の作品は出生の秘密に囚われた内容が多く、それに自虐的な笑いを織り交ぜた俯瞰した視点が笑いを誘いますが、それは漱石が禅や哲学の本を愛好しており、苦を笑いに変える解脱を求めていた証です。
笑いと悩みの原点はどちらも矛盾から生じており、何に矛盾を感じるか? で、その人の教養の高下と深浅が判ると鈴木大拙が書いているのことは漱石に当て嵌ります。
漱石の転機は修善寺での吐血で、病床で意識が回復し始めた時、妻や身の回りの人達の自分への愛情を確信できたことでした。
吐血前の主人公の僻みは全て社会状況のせいにしていた小説から、僻み根性の主人公を責める文体に変化し、愛憎を別にして考える余裕が生まれ、己自身を俯瞰して書くように変化して病後に『彼岸過迄』を執筆しました。
芥川は出生の秘密を避け続けましたが、漱石は生来の愛情への飢えを僻みとして妻に発散し続け、お金の力では支配できない真に偉大なものも求め続けて西洋哲学も含めた学業に励み、自分の中に潜む狂気と神経衰弱を自覚し公言していたことも克服できた理由と思います。
僻みは強烈な自己意識から生まれますが、裏返すと他者の承認を強く求めている感情です。
禅問答のようですが、出生の秘密によって僻みが生じるのではなく、僻みこそが人間の精神(心)の出生の秘密です。
確かに僻みの強弱には、生育環境が大きく係わっていますが、出生の秘密が強いる鋭敏な自己意識をなだめる漱石の手立てになったのは、英国留学時の哲学・心理学の勉強が大きな役目を果たしていました。
その中で一番大きく影響を与えたのがヘーゲルの『精神現象学』で、僻みの部分だけを焦点にして、母の愛をめぐる姉妹を例に簡略に述べてみます。
最初に生まれた娘に妹が生まれた時、母の愛をひとり占めしていた姉が無意識に僻むのは、母親の愛情をひとり占めしたい欲望を、母親に嫌われないように察して抑え込んでいるからです。
つまり僻みは自分を認めて欲しいという欲望を、私はそんなことを望んではいないと自分に言い聞かせて抑圧している時に生じる矛盾した感情です。
自分が求めている母の愛情を意識的に否定し、自分自身に言い聞かせ無理やり自分に承認させる矛盾に陥っている時、自然発生的に僻み根性が起きています。
しかし僻みには、どうして・どうしたら好かれるのだろう?? と考えることに繋がるので『人間は考える葦である』となる思惟の起源に繋がっていると西洋の哲学者は捉えていました。
この欲望と抑圧の矛盾した二重性を溶解してくれるのは、芥川と三島が表現できなかった愛と性で、愛と性から生まれるいい意味の錯覚が僻みをやわらげるのですが、その錯覚には人の心を豊かにも惨めにもする二重性もあります。
人間が生きている限り持ち続ける煩悩は、自我と自己と社会の葛藤によるものですが、これを作家の村上春樹が次のように表現していました。
紙に二重丸を書き、内側の丸の中が自我、内側の丸と外側の丸の間が自己、外側の丸の外の白紙全てが社会であると述べ、真ん中の自己は内側の自我と、外側の社会に挟まれて承認と抑圧に苦しみ、人生において自己を維持するための葛藤が宿命としてあるというような趣旨のことでした。
僻みの反対が素直なら、きっと真に素直な人間など存在しないから、素直は美徳なのだと思います。
生前の妻が事あるごとに、『あなたは小生意気なひねくれ者』と微笑みながら私に言っていたことが頭に浮かんできました。
本を読んでいる時も覗き込み、『小難しい本を読んで、面倒くさいことを考えてるのね!』と微笑み言いながら、私の心の中の危険な部分をかき混ぜ薄めてくれた後、けなした否定の言葉に必ず付け加えるのが、『お父さん頑張れー』という投げやりな肯定の言葉でした。
小難しいことが理解できるから偉いわけでもなく、お互いがお互いを必要として一緒に暮らす愛情を伴う性的な関係の中には、恥部も含めて信頼し支え合っている実感を生み、その実感は錯覚か幻想みたいな危ういものですが、その幻想を錯覚し続ける努力の継続で夫婦の対幻想を実現し、その対幻想が僻みの根源的な欲望と抑圧という息苦しい煩悩を癒し解放して行きます。
 幸せであることを
意識できる生活
幸せであることを
意識できる生活